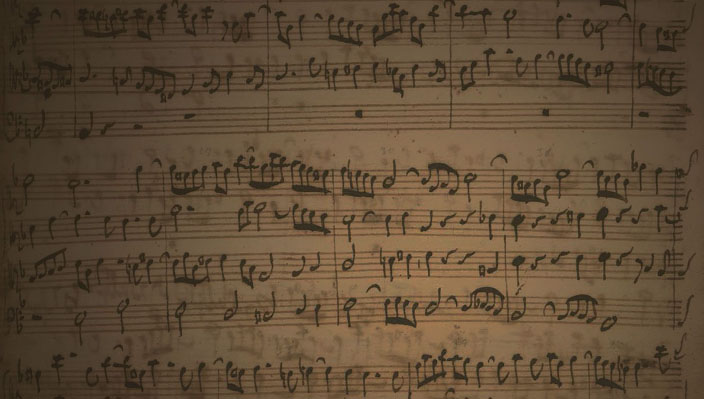RESEARCH
無意識と意識が調和する社会システム
無意識と意識の不調がおこる原因のひとつは、人間が相互作用する社会システムを含む多くのシステムにおいて暗黙的に仮定されている人間のモデルが、システムの巨大化に伴う効率性という尺度への偏重などに起因する限られた視点を基礎としていることだろう。
例えば、現代社会で多用される考え方にナッジングがある。ここでは、人間はただある行動特性をもった機械として「暗黙的」に仮定されがちである。
同様にして、痛みがあるから痛みを止めるという対症療法的思考は、人間が痛みを避け、快のみを求める機械であると「暗黙的」に仮定している。
そこには共通して、自然の作用には深い理由がなく、自意識の判断のほうが正しいという傲慢さがあるといえる。
このような社会システムの中で生きるには、そこで仮定される人間モデルと類似しなくては生きにくいがゆえに我々は知らないうちに機械化し、身体性が次第に鈍化していくと推察できる。そこを解決するためには、人間モデルの忠実度の向上が必要なのである。
それが社会システムのデザインに取り入れられることで無意識と意識の調和の問題を、個々の内面からの変容という側面だけでなく、個を取り巻く環境からの影響という双方からアプローチできると考えている。
それによって、日常という地平で自然に慈悲や観想的学びを取り入れていくことに目を向けさせられるだろう。
以下の各研究において、全体的存在としての人間の理解を深めるための取り組みを行っている。
心と身体のモデルを基礎とした議論
2024年3月7日に慶應義塾大学三田キャンパスで開催された国際シンポジウム
『AI時代の心の教育 〜観想的な学びとコンパッションの日本的展開〜』で、以下のような議論があった。
「欧米で行われる慈悲教育は、日本の伝統文化のなかであたりまえに行われている内容を多く含んでおり、それを新しく西洋化された形で学ぶプログラムをそのまま日本で教えることが適切か?」
この疑問の背景には私たち日本人をはじめとする東洋的視点での身体観が、
西洋のものととは異なるという背景があり、
多くの社会問題に通底する本質的原因を捉える良い機会と考える。
このような疑問が起こるのは、これまでの科学の対象から除外されていたような領域においては、扱われる言葉の定義そのものやそれに伴ったモデルの解像度があいまいであり、一義的に解釈され得ないことに起因していると考えられる。
そこで本研究では、システム思考やモデルベースシステムエンジニアリングを用い、これまで曖昧であった「心」や「身体」を、
- 俯瞰的視点に立って「外部システム」との相互作用を明らかにする
- その際にさまざまな領域の深い感覚と経験に裏付けされた視点を取り入れる
- 1と2に基づいたシステム内部の段階的詳細化
を実施することで、例えば「慈悲」というものが何を意味しているのかということを明確化する。
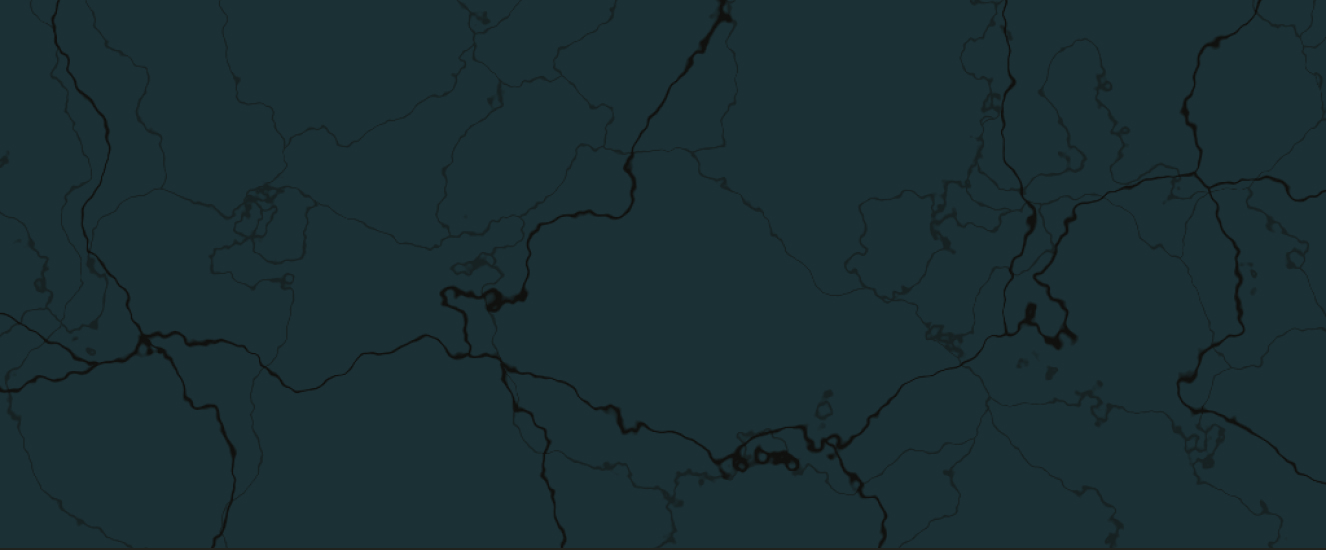
人間の体の偏り、凝集
人は誰しも身体を均等に使っていない。この偏り方に、生命原理に基づく新たな人間理解のための鍵があり、当該知見を深めることが人間の自発性という視点に立ったシステムのデザインに貢献すると考える。
この偏りは腰部の無意識的方向性に現れ、動作や性格の共起性を決定する大きな制約として、人間の感受性を含む個性に影響を与えている。足圧分布計測を用いた測定実験結果は、足圧体圧分布に示される腰部の無意識的方向性が人によって異なった類型をもち、その類型が個人によってある程度一貫して現れることを示唆している。
面白いのはこの偏り方が個の凝集の方向性と関連し、その人を取り巻く現象すべてにその相似形が現れると捉えられる点だ。
こう考えると、例えばアートそのものを凝集と捉えることができる。例えば、音楽というものは音を凝集する行為であるし、自分の部屋をつくり上げていく過程も、自分の要求にあうような物を凝集していく行為といえる。
人間には不思議と、このまとまり感に関する繊細な感性というものが備わっていて、無意識的に意思決定に影響を与えているのだが、意識的に論じられることは少ない。
この「凝集」という視点は、アートや、場作り、組織づくりといった様々な領域に援用可能であり、これまでない知見を生み出す可能性がある。

有機体のシステムと
バッハの音楽
バッハの作品を統計的に分析し完全な再現性をもつAIを実装できたとしても、バッハを理解したことにはならない。それは手法や技法という以前にあって、音楽であればそこに集められた音の集合にある種のまとまりを作り出す凝集力の源となっているものが「生命」であり、「バッハ」の本質であるといえるからだ。
その意味で、音楽とは、モーツァルトの言うように「我々が生きることそのもの」であるとも言えるのである。
我々自身が内的要求の現象化であり、この現象化のプロセスを擬似的に体験することが音楽であるからだ。
大切なのは、「生きること」の方向性というものが人によって異なることであり、それを明らかにすることが「生命」の理解に必要であるということでもある。
まとまりを持った部屋のなかに、ひとつ雰囲気の異なった家具をおいただけで調和が乱されてしまうということがあるように、些細な違いが「まとまり」を乱してしまう。ここに、「創造」の難しさがある。
岡潔のいうように、「破壊」というものは近似によって大雑把な不等式を与えただけでできてしまう。しかし、凝集によってまとまりをつくり出す行為であるとも捉えられる「創造」はそうはいかない。
バッハの音楽に軽微な変更が加えられればそれはバッハでなくなってしまうように、生命や美というものは繊細なものなのであり、だからこそ従来の科学において生命の研究が、記号の研究に置き換えられてしまったのだろう。
そこではやはり「主観」というものが重要となってくる。「主観でない客観」などというものは存在しないのであるが、とくに「客観でない主観」が「生命」の理解に重要となるだろう。 ある種の体感覚を共有する集団によってのみ成立する言語化と、より一般的な集団に共通して成立する言語化の橋渡しがひとつの鍵になる。
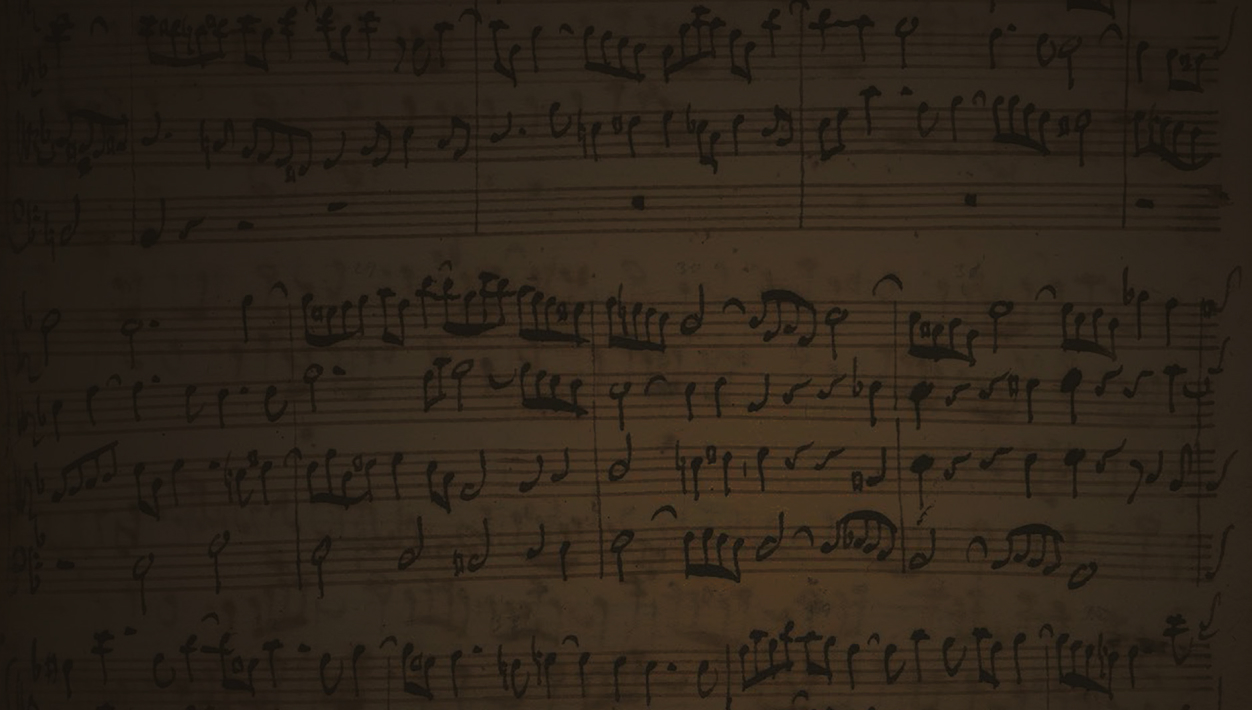
心と身体のモデルを基礎とした
議論
これまでの科学の対象から除外されていたような領域においては、扱われる言葉の定義そのものやそれに伴ったモデルの解像度があいまいであり、一義的に解釈され得ないという問題がある。
システム思考やモデルベースシステムエンジニアリングを用いることで、この問題を解決し、越境的研究を促進できると考える。この際特に重要となる視点は以下の3点である。
- 俯瞰的視点に立った「外部システム」との相互作用分析
- システム内部の段階的詳細化
- 知識だけでなく深い経験と直観による全体的理解に裏付けされた専門家の視点の導入
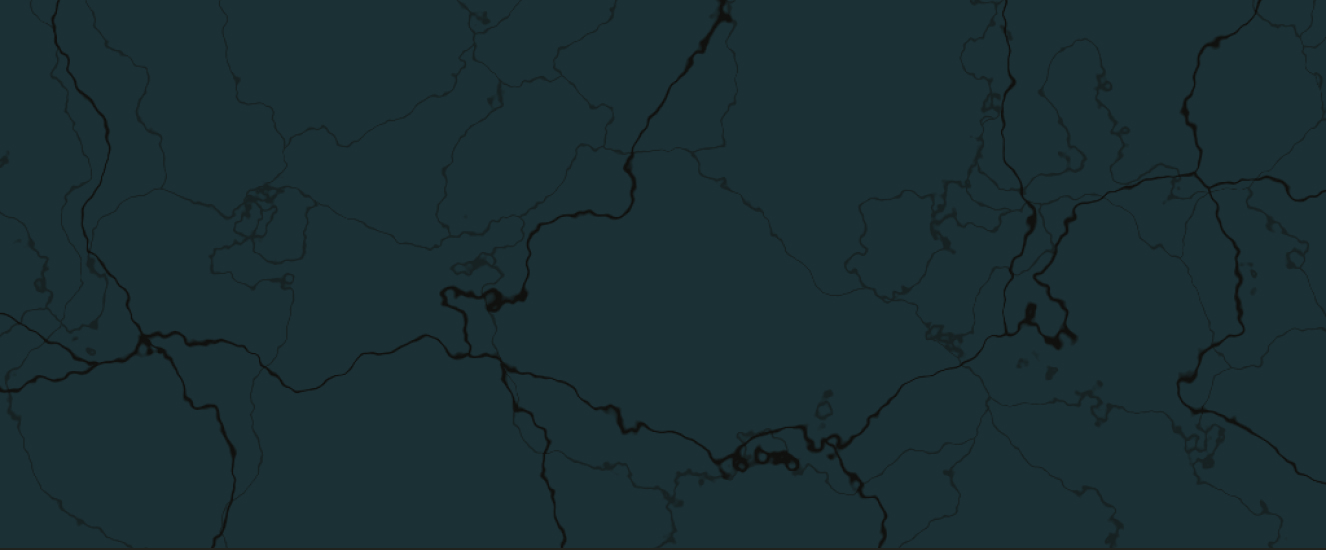
人間の体の偏り、凝集
人は誰しも身体を均等に使っていない。この偏り方に、生命原理に基づく新たな人間理解のための鍵があり、当該知見を深めることが人間の自発性という視点に立ったシステムのデザインに貢献すると考える。
面白いのはこの偏り方が個の「凝集」の方向性と関連し、その人を取り巻く現象すべてにその相似形が現れると捉えられる点だ。
この「凝集」という視点は、アートや、場作り、組織づくりといった様々な領域に援用可能であり、これまでない知見を生み出す可能性がある。

有機体のシステムとバッハの音楽
自己相似形や再帰性、偶発性というものが有機システムの記号論的理解に重要であり、群論やホモロジー代数、圏論などを用いて有機性の発展を論じずることができないか検討する。
しかし一方で、バッハの作品をいかに記号論的に分析し完全な再現性をもつAIを実装できたとしても、バッハを理解したことにはならない。そこには「生命」の視点が必要なのである。記号論的理解にこういった視点を統合する手段を考え、真の有機体の理解を得ることが目標となる。